のんびり天体観測
- 高野
- 2015年4月6日
- 読了時間: 2分
皆さんは、「流星群」を見たことがあるだろうか。それは、その軌跡が天球上のある一点を中心に放射状に広がるように出現する一群の流星のことである。では、「流星」とは何なのか。それは、宇宙空間にあるチリの粒が地球の大気に飛び込んできて大気と激しく衝突し、高温になってチリが気化する一方で、大気や気化したチリの成分が光を放つ現象のことである。チリの大きさは、直径一ミリメートルから数センチメートル程度と、さまざまだ。
主な流星群は、1月上旬に「しぶんぎ座流星群」、4月中旬に「みずがめ座流星群」、7月中旬に「やぎ座流星群」、8月中旬に「ペルセウス座流星群」、同じ8月中旬に「はくちょう座」、10月中旬に「オリオン座流星群」、そして、12月の上旬には「ふたご座流星群」が出現する。そのうちの「しぶんぎ座流星群」、「ペルセウス座流星群」、「ふたご座流星群」は毎年ほぼ確定して多くの流星が出現するため、「三大流星群」と呼ばれている。それぞれの流星群に極大日があり、一時間あたり、最大で80もの流星群が夜空を流れる。
そんな星空を見るために、全国各地で「星空スポット」が紹介されている。なかでも埼玉県ときがわ町の「堂平天文台星と緑の創造センター」は、昭和37年以来「堂平観測所」として日本の天文学を支えてきた施設で、現在ではリニューアルされ宿泊もできる人気スポットである。さらに、「沖縄県石垣島天文台」では、本州では観察の難しい南十字星やカノープスなど、88全星座のうち84星座を見ることが可能である。
忙しい日常から離れ、たまには宇宙の神秘に触れ、静かなひと時を過ごしてみるのもいいかもしれない。
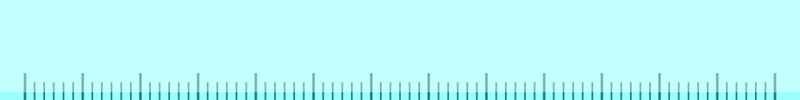
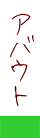
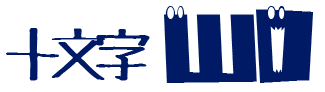

コメント