台風や集中豪雨の猛威 床上浸水、対策法知っていますか
- ざらめ
- 2015年10月6日
- 読了時間: 3分
9月9日、台風18号が日本に上陸した。南から北へ突き抜ける形で横断し、約4時間ほどで日本から去った。しかし、この台風は接近前から温帯低気圧に変わったあと、己が存在する全ての時間をかけて日本に大雨をもたらした。50年に1度の大雨とも称され、茨城県の鬼怒川や山形県の最上小国川など約70もの河川で堤防の決壊や氾濫がおきた。その氾濫や土砂流入により、栃木県内の東武鉄道も被害を受けた。鬼怒川などは堤防決壊後5日経っても水が引かず、避難所生活を余儀なくされた人が大勢いる。
著者は埼玉県東部に在住しているが、ここでも床上浸水を経験した。元々土地が低いこともあり、台風が来るたび床下への浸水はしょっちゅうあったのだが、床上浸水は初めてだ。大きすぎる被害ばかりが報道されているが、こうした小さい被害に遭った家屋も少なくない。床上浸水への対策はどうすればいいのだろうか。
一番ポピュラーなものが土嚢だろう。市役所などに申請すれば頂戴できるが、最近は土ではなく水を使って水嚢を作る事も多い。ごみ袋を2~3重にし、半分くらい水を入れてきつく縛り、玄関前などに置く。土嚢と比べて普段の生活で場所も取らないし、作るのも簡単だ。段ボール箱に入れて使えば強度も増し安定する。水や土でなく、プランターやポリタンクを並べてレジャーシートで包んでも代用できる。しかし、いくら土嚢や水嚢を積んでも隙間やその上を超えて水が襲ってくることもある。その場合、水が引くときに土嚢や水嚢が邪魔になって屋内の水が引いていかないので注意が必要だ。
玄関や窓などに目が行きがちだが、屋内からの浸水にも留意してほしい。排水溝や床下収納などがある部屋ではそこから水が上がってくる可能性がある。風呂場や洗濯機などの排水溝が1階にある場合は水嚢を使って排水溝を塞ごう。湯船に関しては栓をして綺麗な水を溜めておくと水が上がらず、さらに断水時の対策にもなる。床下収納の場合も、扉の上に重い物や水嚢を乗せれば浸水を防げる。トイレは1階でも2階でも水が上がったり詰まったりする場合があるのでこちらも対策を。
床上浸水が避けられない場合は、被害が少なくなるように棚上や2階などにものを移動すると良い。家電など重いものは無理かもしれないが、通帳や財布などの貴重品だけでも移動させるべきだ。濡らしたくないもの、濡らすと後処理が面倒なものも移動できると尚良い。著者宅では床から30㌢ほどの高さにあるものをすべて移動させたため、被害は床と壁、棚のみで済んだ。外出時に浸水してしまったという最悪な事態を生むこともあるが、普段からキャスターや机の上に物を置くなど、物を床置きにしないようにすれば被害も少なくなる。なお、水が引いたあとは掃除だけでなく除菌も忘れずに。
また災害保険の活用も。申請する場合は、浸水したことがわかるような写真や動画を撮影しておくとスムーズに交渉できる。保険だけでなく市役所から補助金がいただけることもあるようだ。のちのち使えるので、余裕があれば被害状況がわかるような証拠を残しておきたいところ。
今回のような大雨ではいかに対策をしても浸水してしまう事があるため、浸水させないことよりも浸水することを前提として動いた方が賢明かもしれない。地震、火山噴火、そして水害。昨今の日本は自然災害が増加している。「うちは大丈夫」という油断は危険極まりない。備えあれば憂いなし、防災対策はやり過ぎて損はないだろう。
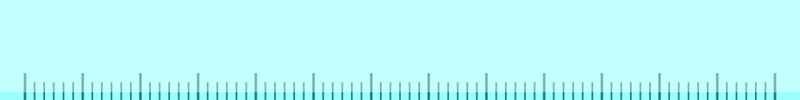
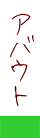
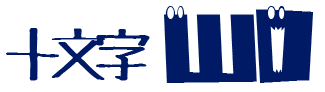

コメント