十文字学園女子大学「J和太鼓部」 受け継がれる歴史
- 高野
- 2015年6月27日
- 読了時間: 3分
和太鼓とは、打楽器の一つである。日本の太鼓の総称で、祭礼、歌舞伎、能、神社仏閣における儀式などに用いられる。皆さんも、一度は目にしたことがあるだろう。華麗な桴さばきに、力強い響き。きっと、誰もが見惚れてしまうだろう。
我が十文字大学女子大学にも、それらを扱う「J和太鼓部」が存在する。今回、部長である3年生の栗原さんに日頃の活動や和太鼓の魅力を聞いた。
活動日は、火曜日と第3月曜日の午後5時50分から。5限終了後、学生たちは皆、動きやすいジャージ服に着替え、そして裸足になる。
普段の主な活動は、「石狩太鼓」、「屋台囃子」、「三宅太鼓」、「ぶち合わせ太鼓」の計4つの練習だという。「石狩太鼓」は、北海道に伝わるもので、北海道上川郡上川町の青年部の若者たちによって30年以上前に創られた太鼓曲である。部員たちは実際の現地の人たちに教えてもらうため、北海道まで合宿に行くそうだ。「屋台囃子」は、12月2日、3日、秩父神社例大祭の付祭りとして奉曳される笠鉾・屋台の内部で演奏されるお囃子で、国指定重要無形民俗文化財にも指定されている。「三宅太鼓」は、三宅島の神着地区に伝わる太鼓芸能で、毎年7月15日前後に行われる牛頭天皇祭で打たれる太鼓。「ぶち合わせ太鼓」は、元々は、三浦半島の先端にある海南神社の祭礼のときに叩かれている太鼓で、その昔漁師たちが村ごとに大漁を祈り、競い合って太鼓を叩き合う、というもの。勝った方にはその年の大漁が約束され、負けた側は太鼓の皮を破られ海に投げ入れられてしまうという言い伝えもあるほど、豊漁を願い村中で心ひとつにして叩かれていた太鼓である。
「一番好きな演奏、得意な演奏は」という質問に栗原さんは、「ぶち合わせ太鼓」だと答えた。「他の演奏とは激しさや迫力が違い、さらに三部構成になっていて面白味があり、何より自分を磨くことができるから」だそうだ。和太鼓の魅力を語る栗原さんは本当に楽しそうだ。
最後に意気込みを聞いた。「期待してくれている人たちに向かって頑張りたい。そして、自分たちの力で成功するために練習する。現在練習している、それぞれの4つの歴史を受け継ぎ、次の世代に渡すことが大切」。みんなで楽しく演奏することを心掛けているそうだ。
北海道に伝わる「石狩太鼓」の演奏を見学させてもらった。5台の和太鼓が用意され、静寂から一変、激しい音と共に部員たちの気持ちが一つになった。その演奏は想像以上に迫力があり、身体に響く重低音は気持ちを高ぶらせる。
「まだまだ完全とは言えない演奏だったが、最後まで演奏できてよかった」。栗原さんは率直に胸の内を明かした。
現在、本学で毎年10月に行われる「桐華祭」での発表に向けて練習している。あの演奏をまた見ることができると思うと、楽しみでたまらない。皆さんも「J和太鼓部」の素晴らしい演奏をぜひ間近で感じていただきたい。きっと、部員たちが魅せる「和太鼓の世界」に引き込まれるはずだ。

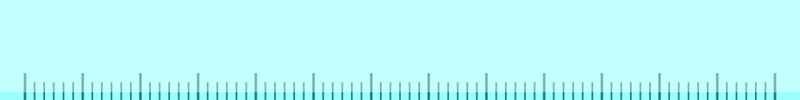
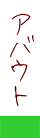
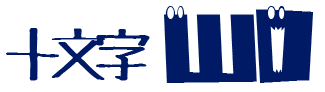

コメント